ささいな歴史を残すこと
日常的に会話がスルーされたり発言が否定されることが多かったためか、こうして原稿を書いてる間も頭のどこかでは「どうせ、誰にも刺さりやしないよ」と冷たい声がしていた。最近、久しぶりにバンプのsupernovaを聴いて「年を数えてみると気づくんだ ささいでも歴史を持っていたこと」という歌詞に、案外自分も捨てたもんじゃないかもしれないと、少しだけ思えた。別に自分のことを否定した社会や周りの人間をゆるしたわけでも、「障害者の権利を守ります」って言葉を完全に受け入れたのでもない。それでも、全部なかったことにして逃げられるよりかはマシだ。社会が「誰ひとり取り残さない」と宣言して、それが誰も居ない世界で達成されたんじゃ意味がない。その約束が果たされたかどうか、この目で見届けなければ。今の自分に何の力がなくても、その価値を決めるにはまだ早いかもしれない。改めて言葉の力を信じてみようと思えた。

今の社会を支えているのは誰でしょう?
子どものうちに障害特性が見つかっても、大人になってから特性がわかっても、進むライフステージは変わらない。ただ、子どもと高齢者に比べて、大人の悩みが相談できる場所は格段に減る。何だかんだ、高齢者になるまでの時間が人生の中で一番長く、仕事でも生活でも悩みを抱えることが多いのだ。就労支援か生活支援かなんて細かく分類しなくても、大人にはここといった一本化した窓口がもっとあっても良い。そもそも、自分が何に困っているかはっきりした状態で相談に行く自体が稀だ。実際は、どこに相談したらいいかわからないままとりあえず話しを聞きに行くことがほとんど。それに、自分のことを説明するのが苦手な人は、ただ相談に行くだけでも結構ハードルが高い。相談する内容でこうも窓口が分散していると、経緯を話すだけで時間がかかって中々本題にたどりつけない。個人の状態や抱える問題が複雑になればなるほど、これまでのように、子どもか高齢者あるいは障害者という区別だけでは対応しきれないんじゃないかと思う。必要なのは、助けを求めたら、それを流さず受け止めてくれること。それさえちゃんと機能していれば、存在が消されそうな恐怖に怯えることもなくなる。ただでさえ、誰の手も借りずに生きることは不可能に近いのだ。だったら、それを見越してできる範囲で手助けできる方が自分にとっても社会にとってもずっと有意義と思う。私は、これまで手を貸してもらった分とこの先助けてもらう分、今この瞬間から他人を助けるくらいでトントンだと考えている。子育てにしたって介護にしたって社会に重要な役割を担っているその間にいる世代だ。その世代が満足に生きられない社会は、基礎工事が整っていない家みたいに、ちょっとしたことで簡単に崩壊してしまう。支え合いで豊かに暮らせることが証明できれば、争いや分断も自然となくなっていいと思う。そのためにも、ともに寄り添える社会を一緒に作る仲間が必要なのだ。
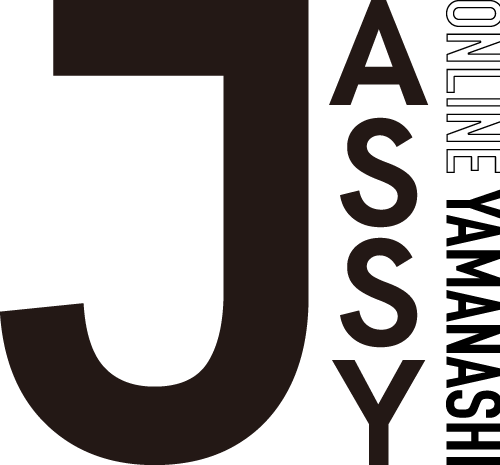



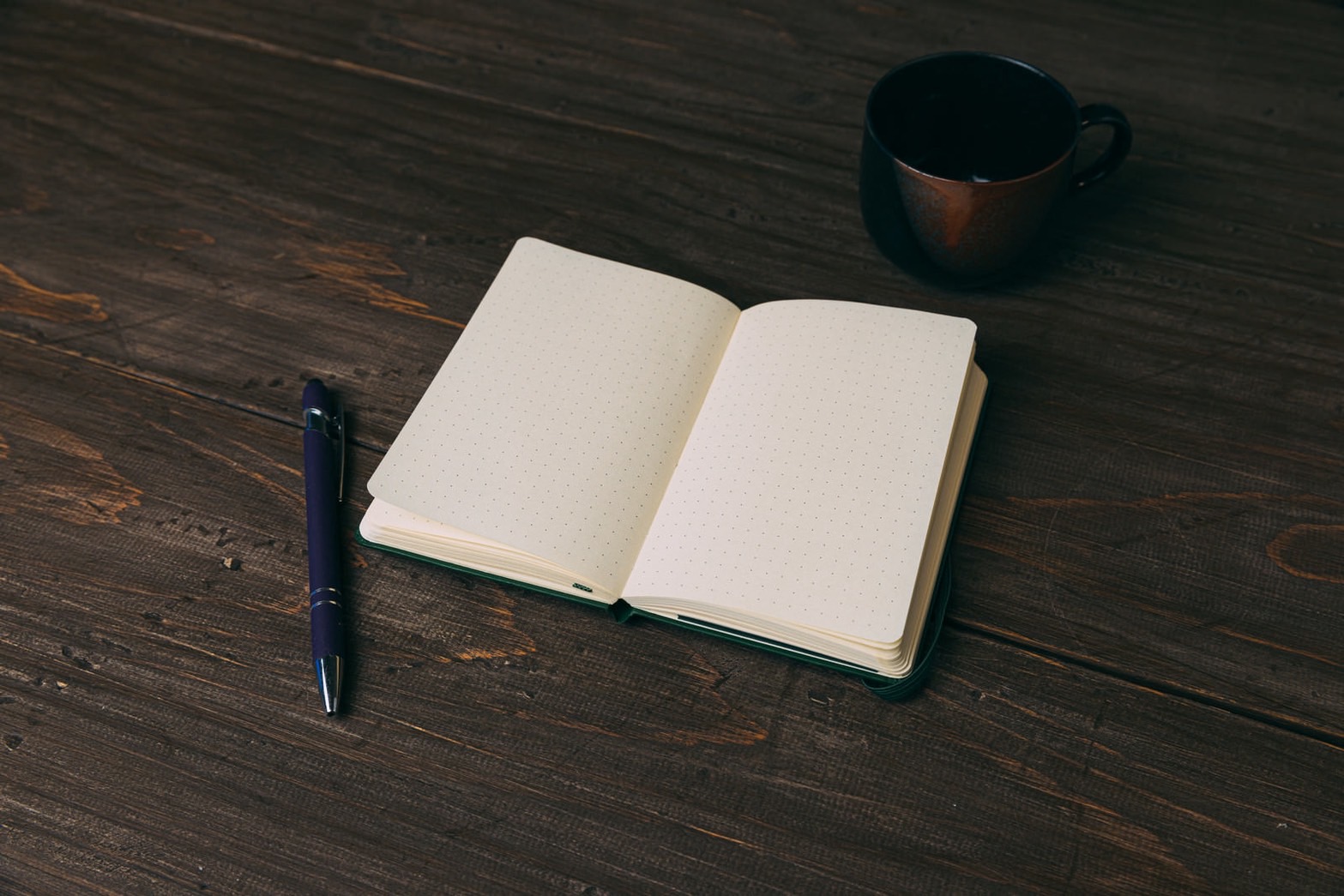
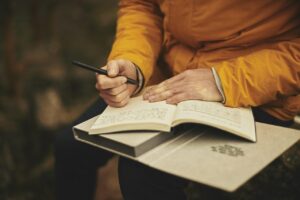



![[2025年12月5日(金)開催]忘年会だョ!全員集合](https://jassy.online/wp-content/uploads/2025/10/忘年会2025_2400x1600-300x200.jpg)
